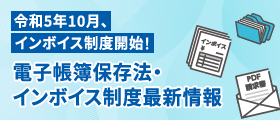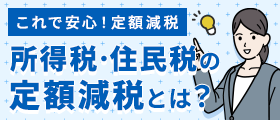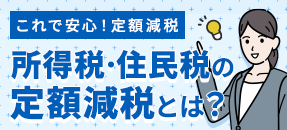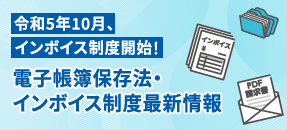巡回監査時の当事務所の支援により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになります。経営者の意思決定に役立つ情報、黒字決算につながる情報が入手できます。

「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)による自計化を支援します。また、継続MASシステムを使用した経営計画策定をご支援します。

自計化と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

| 2023年 11月 14日 | 伏見納税協会で「簿記教室」の講師(4日目)を勤めました。 |
| 2023年 11月 7日 | 伏見納税協会で「簿記教室」の講師(3日目)を勤めました。 |
| 2023年 10月 31日 | 伏見納税協会で「簿記教室」の講師(2日目)を勤めました。 |
| 2023年 10月 24日 | 伏見納税協会で「簿記教室」の講師(1日目)を勤めました。 |
| 2023年 10月 5日 | 事務所公式LINEアカウント開設しました(当ページ下部に友達追加ボタンを設置しています) |
| 2023年 8月 24日 | 巡回監査士(補)相続税法講師(2日目)をつとめました。 |
| 2023年 8月 17日 | 巡回監査士(補)相続税法講師(1日目)をつとめました。 |
| 2023年 7月 27日 | 名古屋芸術大学で非常勤講師をつとめました。(2023年前期/4月~7月) |
| 2023年 2月 2日 | 京都新聞(京滋版)、朝日新聞(京都版・滋賀版)、読売新聞(京都版・滋賀版)に新聞名刺広告を掲載しました。 |
| 2023年 1月 28日 | 名古屋芸術大学で「簿記入門講座」の講師を務めました。 |
| 2023年 1月 1日 | 近畿税理士会のCMにエキストラ出演しました(当ページ下段YouTube動画 参照) |

|
2024年 4月 1日 |
|
|
2024年 3月 31日 |
|
|
2024年 3月 30日 |
|
|
2024年 3月 29日 |
|
|
2024年 3月 28日 |
|
|
2024年 3月 27日 |
|
|
2024年 3月 26日 |
|
|
2024年 3月 25日 |
|
|
2024年 3月 24日 |
|
|
2024年 3月 23日 |
|
|
2024年 3月 22日 |
|
|
2024年 3月 21日 |
|
|
2024年 3月 20日 |
|
|
2024年 3月 19日 |
|
|
2024年 3月 18日 |
|
|
2024年 3月 17日 |
|
|
2024年 3月 16日 |
|
|
2024年 3月 15日 |
|
|
2024年 3月 14日 |
|
|
2024年 3月 13日 |
|
|
2024年 3月 12日 |
|
|
2024年 3月 11日 |
|
|
2024年 3月 10日 |
|
|
2024年 3月 9日 |
|
|
2024年 3月 8日 |
|
|
2024年 3月 7日 |
|
|
2024年 3月 6日 |
|
|
2024年 3月 5日 |
|
|
2024年 3月 4日 |
|
|
2024年 3月 3日 |
|
|
2024年 3月 2日 |
|
|
2024年 3月 1日 |
ここに見出しを入力してください

ここに見出しを入力してください
ここに見出しを入力してください


💡知って得する税務会計の情報などを定期的に配信いたします💡
友達登録は右記QRコードから、または、当ページ下段の「友だち追加ボタン」からお願いいたします。